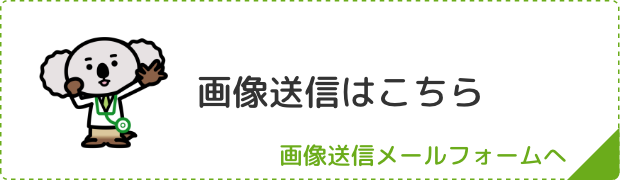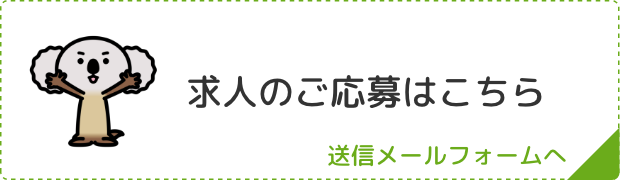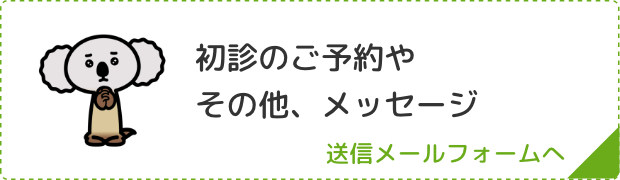よくある質問
FAQクリニックの利用案内
最寄り駅から近いですか? 駐車場はありますか?
西武新宿線 狭山市駅西口から徒歩3分です。スカイテラス商業施設の3階にあります。
提携している駐車場はありませんので、サービス券などのお渡しはありません。狭山市駅西口駐車場がスカイテラス商業施設と繋がっています。
詳しくは、狭山市役所 ホームページをご確認ください。
整形外科的なケガ(転倒・腰痛など)も診てもらえますか?
かかりつけの方であればいいのですが、新規の患者さんは整形外科に受診して下さい。
院長のYouTubeを見ました。どんな治療が受けられますか?
当院では、関節リウマチと膠原病に関する包括的な治療を受けることができます。
具体的には、最新の薬物療法(メトトレキサートなどの抗リウマチ薬、生物学的製剤、JAK阻害薬すべて)を提供しており、必要に応じてリハビリテーションや整形外科的処置との連携も行います。また、エコー・X線・CTなど先進の検査設備を備え、正確な診断・効果判定を行っています。院長のYouTubeでは当院の治療方針や最新情報について発信しておりますが、ご覧いただいたとおり、当院はリウマチ専門医が中心となり総合的なケアを提供しています。例えば、生物学的製剤に関しては全種類取り扱い可能であり、お一人おひとりに最適な薬剤を選択します。さらに、リハビリ専門スタッフによるリウマチ特化型リハビリを行い、関節の機能維持・回復にも力を入れています。呼吸器合併症や骨の問題があれば、連携する呼吸器内科医・整形外科医と協力して診療します。
小児リウマチにも対応可能です。
要するに、「リウマチかな?」という初期診断から最新治療、生活支援までワンストップでサポートできるのが当院の強みです。
他の病院から転院を考えています。どうすればいいですか?
当院への転院をご希望の場合、まず現在かかっている医療機関から紹介状(診療情報提供書)を作成してもらってください。
紹介状と最新の検査結果をお持ちのうえ、当院の予約をお取りいただければスムーズに引き継ぎができます。初診時には紹介状以外に健康保険証やお薬手帳も忘れずにご持参ください。転院に際しては、現在の治療を中断しないことが大切です。予約日は余裕をもって設定し、現在の主治医に次回受診日までの薬を多めに処方してもらうようお願いしましょう。「転院希望」であることを伝えていただければ、可能な限り早い日程をご案内いたします。
転院後はこれまでの治療を踏まえつつ、より良い状態を目指して診療を継続します。今まで困っていたことや不安な点があれば、遠慮なく新しい主治医にお話しください。
通院・費用・支払い
治療費や薬代が高くて続けられそうにありません。何か制度はありますか?
日本では関節リウマチは公費助成の対象となる場合があります。具体的には、症状が一定以上であれば指定難病医療費助成制度を利用でき、自己負担額が軽減されます。また、所得に応じて高額療養費制度が適用され、月々の医療費自己負担には上限が設けられます。これらの制度を活用すれば、高額な生物学的製剤などの治療も継続しやすくなります。 関節リウマチは現在、「指定難病(膠原病系)」に指定されており、所定の手続きを経て受給者証を取得すれば医療費の自己負担割合が原則2割もしくは軽減額の設定などを受けられます(所得水準により異なります)。また、高額療養費制度により1ヶ月の自己負担が一定額を超えた場合、超過分が払い戻されます。たとえば生物学的製剤で月数十万円の費用がかかっても、多くの方は高額療養費制度で自己負担は数万円程度に抑えられています。その他、障害年金(関節機能に重度の障害が残る場合)や介護保険(要支援・要介護認定)など、経済面を支える制度は複数あります。治療費の心配がある場合は、当院の医療ソーシャルワーカーや事務スタッフにご相談ください。申請方法や条件について丁寧にご案内し、必要書類の作成(診断書等)もお手伝いいたします。
保険は効きますか? 公的補助は受けられますか?
関節リウマチの診療は健康保険が適用されます。診察や検査、処方される薬剤(生物学的製剤やJAK阻害薬も含め)も保険適用であり、通常は3割負担(※年齢や所得によって1割または2割の場合も)です。さらに、公的補助としては前述の指定難病医療費助成制度や高額療養費制度を利用できます。これらを適用すると患者さんの自己負担額が大きく減ります。生物学的製剤やJAK阻害薬は1剤あたり月数十万円する高額な薬ですが、保険適用内ですので患者さん負担はその一部になります。例えば、月に薬剤費30万円の場合、3割負担なら9万円ですが、高額療養費制度によって所得区分に応じ上限(例えば一般所得の方で約44,400円+α)が設定されます。また、指定難病の助成を受けられればさらに負担が軽減されます。要件を満たせば公的補助を重ねて受けることも可能です。適用可否については主治医が診断書を作成し、各自治体の窓口で申請します。当院でも手続きのサポートをいたしますので、遠慮なくご相談ください
血液検査は毎回必要ですか?
各お薬の添付文書には開始後2週間ごとに検査をして副作用が出ていないか確認するように記載されています。
その後、副作用が出ていないことを確認しつつ当院では4~6週(厚労省の指示では原則30日処方)で処方を継続します。
皆さんを怖がらせるつもりはありませんが、薬というものは作用があって副作用もある。そこを注意しながら薬の効果を期待しながら
医師は処方をしています。何と言っても、皆さんが使用している薬は免疫に関わるお薬です。
病気はよくなったけど、副作用で他の臓器にトラブルが出てしまったということでは困るわけです。
いつも変わりないと言われるのにそんなに検査が必要ですか?と聞かれる方が居りますが、毎回何でもないことがとても安心です。
少しでも異常値が見られたら早めに対応したいのでご協力ください.
レントゲンやCT、エコーなどの検査はどれくらいの頻度で行うの?
頻度は特に決まっていません。検査値の異常や症状で何か疑わしい時に確認のために適宜行います。
治療がスムーズにいかないケースにおいては、色々と治療を微調整したり変更したりしますので、評価のために血液検査と併せて行います。
頻繁に検査することが納得いかない時は主治医とご相談ください。その必要性について説明してくださいます。
治療がスムーズにいって寛解導入出来た方でも年に1回は確認させて頂きます。
経済的な理由で治療をためらっています。相談できますか?
はい、遠慮なくご相談ください。経済的な不安から治療を躊躇している場合、主治医や看護師に現状を伝えることが第一歩です。薬代の負担が重い場合は、公的助成制度の利用を検討しますし、薬の種類をジェネリック医薬品に変更するなど負担軽減策も考えられます。 医療費の問題で治療を中断してしまうと症状が悪化し、結果的に入院や手術が必要になってさらに費用がかかる恐れもあります。そうなる前に、ぜひ病院側と対策を話し合ってください。
当院では外来時の相談を通じて経済面の悩みを受け付けています。場合によっては福祉事務所と連携し、生活保護や障害年金などの制度の紹介も行います。治療をためらうほどの経済的負担を感じていること自体、重要な情報ですので、必ずお伝えください。患者さんが安心して治療を続けられるよう、一緒に解決策を考えていきます。
クレジットカードや電子マネーは使えますか?
クレジッドカードは、VISA・master・JCB・AMERICANEXPRESS・DinersClub・DISCOVERが使用できます。また、電子マネー決済・バーコード決済もご利用いただけます。
2025年4月よりクレジットカードの限度額により、暗証番号が分からないとご利用いただけないことがありますので、ご了承ください。
予約制ですか? 紹介状は必要ですか?
予約制ですが、当日ご受診希望の場合は、一度お電話ください。紹介状については、なくても大丈夫ですが、あった方がいいです。
診察なしで薬だけもらうことはできますか?
診察をしない(無診察)で、お薬を出すことはできません。必ず医師による診察を受診していだきます。どうしてもご本人がいらっしゃれない場合は、ご家族の代理受診も可能です。一度ご相談ください。
通院が難しい場合・訪問診療
夜間や休日に急に困ったときはどうすればいいですか?
夜間や休日に症状が悪化した場合、いくつかの対処法があります。
まず、命に関わるような症状(激痛で動けない、胸の痛みや息苦しさ、意識障害など)の場合は躊躇せずに救急病院を受診してください。関節リウマチそのものの急な悪化であれば、夜間休日でも当番の総合病院で痛み止めの処方や必要な処置を受けられます。軽症で救急に行くほどではないが不安な場合は、当院のリウマチコール(電話相談サービス)に連絡し、アドバイスを受けることも可能です。リウマチ患者さんは免疫抑制剤を使っていることもあり、発熱した場合などは感染症のリスク評価が重要です。39℃以上の高熱や激しい痛みが夜間に出現した場合は、無理に我慢せず救急受診するほうが安全です。その際、救急医に「リウマチで〇〇の薬を使用中」であることを伝えてください。休日についても同様で、地域の救急当番医や病院を利用しましょう。
一方で、「明け方に少し手がこわばる」「薬を飲み忘れて関節が少し痛む」程度であれば、次の診療日まで自宅で安静・様子見でも大丈夫なケースが多いです。市販の痛み止めでしのげる場合もあります。判断に迷うときのために当院では患者さん直通の相談窓口(リウマチコール)を設けています。夜間休日でも対応時間内であれば電話で指示を仰げますので、不安な際は活用してください。
高齢でひとり暮らしですが、通い続けるのが心配です。対応はありますか?
高齢の一人暮らしの患者さんでも治療を継続できるよう、当院では様々な支援策を講じています。
まず、オンライン診療を活用すれば通院回数を減らすことが可能です。
また、病状が安定していれば処方日数を長くして来院頻度を調整することもあります。どうしても来院が難しい場合は、在宅医療機関と連携して訪問看護師によるフォローや、必要時の医師往診を調整します。ご高齢で交通手段がない方には、地域の送迎サービス(行政やボランティアによる車の手配など)を案内することもできます。また、デイケアやデイサービス利用中に当院のリハビリを組み合わせるなど、介護サービスとの連携も可能です。お一人で不安な場合、主治医がご家族と連絡を取り合い病状を共有することもできます。例えば離れて暮らすご家族に電話で説明したり、必要に応じて診療情報提供書を書いて近隣の医院と情報共有するケースもあります。「通院が負担で治療をやめてしまいたい」と思う前に、ぜひ我々医療者に相談してください。
患者さんの生活環境に合わせた治療継続プランを一緒に考えます。
生活・日常動作について
痛みがあるときでも、運動していいのでしょうか?
痛みがあっても、炎症が過度に強くない場合は、適度に身体を動かすことがむしろ関節や筋肉の機能維持に役立ちます。完全に安静にしてしまうと、関節拘縮や筋力低下を招いて痛みの悪化につながるおそれがあります。
関節リウマチなどで痛みを感じるときは、まったく動かさないと関節がかたくなり、筋力が衰えてしまいます。その結果、将来的に動ける範囲が狭まり、痛みも改善しにくくなる可能性があります。激しい腫れや炎症があるときは一時的に安静が必要ですが、軽度〜中等度の痛みであれば、主治医やリハビリスタッフと相談しながらストレッチや軽い有酸素運動を続けることで、可動域の維持や血流改善を図り、長期的には痛みを抑える効果も期待できます。無理をせず、自分の症状に合わせて少しずつ運動量を調整しましょう。
痛む関節は冷やすほうがいい? それとも温めるほうがいい?
急性的な熱や腫れを伴った痛みの場合は炎症を鎮静化するために冷やすことをお勧めします。
注意として冷やしすぎは禁物です。関節の冷えやカイロなどによる低温火傷などのトラブルに気を付け、
冷やすときは5分ずつくらいを3クール、なお湿布は冷やす効果はないのでアイスノンなどを使用してください。
どちらか分からない時は自分が気持ちよいほうで構いません。
仕事や家事は続けられますか?
適切に治療すれば、多くの方は仕事や家事を続けることができます。リウマチ治療の目標は発症前と同じような日常生活を送れる状態に戻すことです。
ただし、症状が強いときは無理をせず、主治医と相談しながら過度な負担を避ける調整も必要です。 かつてはリウマチになると仕事を辞めざるを得ないケースもありましたが、今や薬物療法の進歩で職業生活を続けることも充分可能になっています。実際に、治療により痛みや腫れが取れて寛解に達すれば、フルタイムで働いている患者さんも多数います。ポイントは、症状の波に合わせて休息を取りつつ活動することです。疲れたら適宜休む、重い物は周囲に頼む、といった工夫をしながら上手に仕事や家事と付き合っていきましょう。
必要であれば主治医に診断書を書いてもらい、職場で業務調整(時短勤務や仕事内容の変更)について相談することもできます。
趣味や運動はやめなければいけませんか?
いいえ、適度に続けて構いません。むしろ無理のない範囲での運動は関節リウマチのリハビリに有効とされています。
趣味も生活の質を高める大切な要素ですので、痛みがひどくならない範囲で続けてください。関節リウマチだからといって安静にしすぎると、筋力低下や関節の拘縮(かたくなること)を招きます。医師から安静指示が出ていない限り、ストレッチや軽い体操などで筋肉を維持することが大切です。例えばウォーキングや水中運動は関節への負担が少なくお勧めです。一方、関節に激しい衝撃が加わるスポーツ(ランニングやジャンプを繰り返す運動)は控え、どうしても行いたい場合は主治医に相談しましょう。趣味活動も、続けることでストレス発散になりメンタル面のプラスになります。痛みが強い日は休むなど調整しつつ、病気とうまく付き合いながら好きなことを楽しむことは治療の一環と考えてください。
タバコやお酒は控えたほうがいいですか?
はい、控えることを強くお勧めします。タバコは関節リウマチの発症リスクを高め、病状を悪化させる要因とされています。
また治療薬の効果を妨げる可能性もあるため禁煙が望ましいです。お酒も大量摂取は避け、特にメトトレキサートなど肝臓に影響を与える薬を服用中は節酒してください。喫煙は関節リウマチの環境要因リスクの代表です。喫煙者は非喫煙者に比べリウマチになりやすく、またリウマチになってからも関節破壊の進行が早いとの報告があります。可能なら禁煙外来なども利用して断煙しましょう。アルコールについては、適量であれば必ずしも禁忌ではありませんが、週に何回も多量に飲む習慣は控えるべきです。飲むなら週にビール1~2本程度までにとどめておくのが無難です。主治医に相談すれば、肝臓への影響を定期的にチェックしながらであれば少量の飲酒を許可してくれる場合もあります。いずれにせよタバコは×、お酒はほどほどが原則です。
食事で気をつけたほうがいいことはありますか?
食事は体に取り込む栄養源です。
好きなものを好きなだけ食べるのではなく、栄養を意識しましょう。Ω3脂肪酸・たんぱく質・ビタミンなどが推奨されています
骨粗しょう症の薬はいつまで飲む必要がありますか?
治療はずっと続ける必要があります。お薬については効果と副作用をみながら変更することがあります。
骨粗鬆症の治療の目的は骨折予防であり、そのためにはお薬だけに頼らず運動や栄養も併せて取り入れる必要があります。
転倒は骨折リスクを上げるので、転ばない身体作りが重要です。
痛みがなくなっても、元のように動けないのはなぜですか?
痛みが治まった後に動かしにくさが残るのは、炎症による関節や筋肉のダメージが影響している可能性があります。
リウマチの炎症で関節の構造が傷んだり、痛みで長期間安静にしていたことで筋力が低下したり関節が硬くなっていることが原因です。 関節リウマチでは、炎症が強いときに関節を動かさないようにしていた結果、周囲の筋肉が痩せたり関節包や腱が硬縮して可動域制限が残ることがあります。また、炎症による軟骨や骨の破壊が起きていた場合、痛みが消えても関節の変形や摩耗によって以前のようなスムーズな動きができないこともあります。こうした場合、リハビリテーション(運動療法)が重要です。ストレッチや筋力トレーニングで弱った筋肉を強化し、関節の柔軟性を高めることで徐々に可動域を回復させます。
主治医や理学療法士と相談し、無理のないリハビリ計画を立てて取り組みましょう。
更年期で不安定ですが、リウマチと関係はありますか?
更年期のホルモン変動がリウマチの発症や症状に影響を及ぼす可能性は指摘されていますが、直接の原因というより間接的な要因と考えられます。
実際、関節リウマチは40~50代の女性に好発し、この時期は更年期と重なるため症状の変動が起きやすいです。女性ホルモン(エストロゲン)は免疫系と関係があり、エストロゲンが減少する更年期には自己免疫疾患の活動性が変化することがあります。一部の患者さんでは更年期にリウマチ症状が悪化したり、逆に発症後に妊娠すると症状が和らぐ(出産後に再燃しやすい)という報告もあります。これはホルモン環境の変化が免疫のバランスに影響するためと考えられています。ただ個人差が大きく、全員に当てはまるわけではありません。更年期で気分や体調が不安定な場合、リウマチ症状とも絡み合ってつらさが増すことがあります。当院では女性専門外来を設け、月経周期や更年期のゆらぎによる症状悪化の相談にも対応しています。
ホルモン補充療法の適否なども含めて、遠慮なくご相談ください。
気持ちが落ち込むのですが、精神面のサポートはありますか?
はい、当院では精神面のサポートにも配慮しています。
スタッフに気軽に気持ちを打ち明けていただければ、必要に応じて専門の心療内科やカウンセリングを紹介したり、患者さん同士が交流できる場をご案内できます。また、診療時間外でも相談できるリウマチコール(電話相談)の体制を整えており、不安な時に直接医療者とコミュニケーションが取れるようにしています。慢性疾患であるリウマチでは、痛みや不安からうつ状態になる患者さんも少なくありません。気分の落ち込みに対しては、早めに対処することが大切です。医師や看護師に相談することで、話を聞いてもらうだけでも心が軽くなることがありますし、必要があれば抗うつ剤の処方や専門医紹介も行います。また、リウマチ友の会など患者会に参加して同じ病気の仲間とおしゃべりすることも精神的支えになります。
当院の「患者さんのための取り組み」として、電話相談の他にも定期的な患者交流会の情報提供(リウマチ患者が集う友ページ参照)などもしていますので、遠慮なくお問い合わせください。
詳しくはこちら
不安や気持ちへのサポート
リウマチと言われてショックです。どう受け止めればいいでしょうか?
リウマチの診断を受けたとき、ショックを感じるのは当然の反応です。
まず知っていただきたいのは、現代の治療では関節リウマチは十分コントロール可能であり、適切に治療すれば発症前とほぼ同じ生活を送ることも可能だということです。焦らずに、主治医や看護師と相談しながら少しずつ病気について理解を深めていきましょう。診断直後は「この先どうなるのか」「仕事や家族は…」など不安が渦巻くかもしれません。
しかし、現在のリウマチ治療はかつてなく発展しており、多くの患者さんが寛解を達成しています。まずは主治医から今後の治療計画(どんな薬を使うか、目標は何か)についてしっかり説明を受けてください。不安なことはメモして質問しましょう。また、必要以上にインターネットの体験談などを読んで心配しすぎないことも大切です(古い情報もあります)。どうしても気持ちの整理がつかない場合、医療ソーシャルワーカーやカウンセラーと話をするのも有効です。幸い、この病気は患者数も多く、情報や仲間も得やすいです。
「一人で抱え込まない」ことを意識し、周囲のサポートを借りながら前向きに取り組んでいきましょう。
痛みが強くて夜眠れないときは?
夜間の強い痛みに対しては、我慢せず対処しましょう。まずその場しのぎとしては、頓服の痛み止め(NSAIDsやカロナールなど)を服用したり、患部を温めたり冷やしたりしてみてください。それでも眠れないほど辛い場合は、翌日でも構いませんので主治医に連絡し、鎮痛剤や炎症止めの調整をお願いしましょう。必要に応じて一時的にステロイドの増量や麻薬系鎮痛薬の処方を検討することもあります。解説: 関節リウマチの痛みがコントロールできていない状態ですので、治療戦略の見直しが必要です。
具体的には、現在の薬の効果が不十分と考えられるため、メトトレキサートの増量や生物学的製剤への変更など根本治療の強化を検討します。同時に、痛みで睡眠不足になるとさらに痛みを感じやすくなる悪循環がありますので、短期的に睡眠導入剤を使うこともあります。夜間痛がある場合、日中も関節炎が続いている可能性が高いですから、遠慮なく医師にその状況を伝えてください。
医師は症状を聞いて、例えば「夜中に痛みで起きるほどです」と言われれば痛み止め追加やステロイド注射など即時対処を考えます。リウマチの痛みは必ず軽減できますので、「夜眠れない」という深刻な状態は我慢せずお知らせいただくことが重要です。
治療しても良くならない気がして不安です…
治療の効果を実感できず不安になるお気持ちはよく分かります。
関節リウマチの治療効果が出るまでには少し時間がかかることもありますし、場合によっては治療法の変更が必要なこともあります。しかし現在は使える薬がたくさんあり、効き目のある治療に必ずたどり着けますので諦めないでください。例えばメトトレキサートは効果発現に数週間~2ヶ月ほどかかりますし、生物学的製剤も投与後すぐに劇的改善というより数回投与してから効力を発揮するものがあります。
また、ある薬で効果不十分でも他の作用機序の薬に切り替えれば驚くほど良くなるケースもあります。大事なのは主治医と目標を共有し、定期的に病状評価(関節の腫れ・痛み、血液検査など)を行って治療を軌道修正することです。3~6ヶ月治療して明らかな改善がなければ、遠慮なく「次の手立て」を相談しましょう。医師も効果が出ていないと判断すれば、生物学的製剤の変更や併用療法など次のプランを提案してくれるはずです。
不安な気持ちは一人で抱え込まず、「良くなっていない気がする」という正直な感覚を伝えることが、より良い治療につながります。
病気を忘れて過ごす時間が欲しいのですが、何かサポートはありますか?
当院では、患者さん同士が交流できるサポートグループやイベントの情報提供を行っています。
例えば、リウマチ患者会(リウマチ友の会)のおしゃべりサロンや交流会に参加することで、病気のことを気にせず趣味や談笑を楽しむ時間を持つことができます。実際にリウマチ友の会主催のイベントに当院スタッフが講師として招かれるなど、患者さんの集まりを支援しています。長い闘病生活では、病気のことを忘れてリフレッシュする時間がとても大切です。当院には専用のサロンルームこそありませんが、院内掲示板やホームページを通じて地域の患者会の案内を掲示しています。リウマチ友の会ではおしゃべりサロンの他に料理教室や体操教室、バス旅行など様々なイベントが企画されています。
そうした場では病気のことは一旦脇に置いて、同じ境遇の仲間と楽しい時間を過ごせます。また当院のリハビリスタッフも、リウマチ体操教室(オンライン配信含む)で楽しみながら身体を動かすプログラムを提供しています。ぜひこれらを活用して、「患者」ではなく一人の人間としてリラックスできる時間を持ってください。
この先、どれくらい長く生きられますか?
関節リウマチそのものが寿命を直接縮めることは基本的にほとんどありません。適切に治療すれば、健常な方とほぼ同じ寿命が期待できます。
実際、現在の治療で寛解が得られれば、関節リウマチになる前と同様の生活が送れます。 かつてはリウマチを患うと心臓病などの合併症リスクが高まり平均余命が短くなると言われた時代もありました。
しかし、生物学的製剤の登場以降、予後は飛躍的に改善しています。大規模データでも、しっかり治療を受けているリウマチ患者さんの生存率は一般人口と大差ないという報告があります。もちろん個人差はあり、感染症や肺合併症など注意すべき点はありますが、定期フォローと適切な管理を続ければ過度に心配する必要はありません。
将来の見通しとしては、治療のさらなる進歩も期待できますし、医師と二人三脚で病気をコントロールしていけば寿命よりもむしろ「どう充実した人生を送るか」を考えられる状況になっていくでしょう。
病気を受け止められない、気持ちが落ち込みます。どこで相談できますか?
そのようなお気持ちはぜひ医療者か専門家に相談してください。
当院では診察時に気持ちの面も含めてお伺いしますし、必要に応じて心療内科や精神科の紹介も行っています。
また、自治体には患者さんのメンタル相談窓口や支援団体もあります。まずは主治医や看護師に「受け止められないほどつらい」と伝えてみてください。 病気の受容は人それぞれペースが違います。無理に前向きになろうとしても難しい時はあります。その場合、専門のカウンセリングを受けるのは有効な手段です。心理士と話すことで、自分の気持ちを整理し、病気と付き合うヒントが得られるかもしれません。
また、同じ病気の仲間の体験談を聞くことも励みになります。リウマチ患者会では電話相談を受け付けていたり、会報でメンタルヘルス特集が組まれたりしています。重要なのは、一人で抱え込まないことです。周囲の家族や友人でも構いませんし、医療ソーシャルワーカーという相談員に話すこともできます。当院のリウマチコールでも日中であれば看護師が相談に乗ります。自分が感じている不安や絶望感をまず誰かに言葉で表してみてください。そこから必ず状況は良い方向に動き始めます。
どうかあなた一人ではないことを忘れないでいてください。
妊娠・出産・女性の悩み
リウマチや膠原病でも妊娠・出産はできますか?
リウマチ疾患のために妊娠出来ないということはありません。しかし、関節炎のコントロールが悪いと妊孕性(妊娠しやすさ)は
下がるため妊娠しづらい事があります。リウマチ以外の膠原病については妊娠の管理に注意を要する疾患もあります。
また、疾患がある・ないに関わらず妊娠・出産・育児は母体に大きな負担をかけるので周囲の協力と理解を得ることも重要です。
生まれてくる命に対する責任が伴います。
妊娠中にリウマチの薬を飲んで大丈夫ですか?
妊娠中に使用できる抗リウマチ薬もありますが、薬によって安全性が大きく異なります。例えばメトトレキサート(MTX)は胎児に有害なおそれ(流産、催奇形性)があるため、妊娠の予定がある方や、妊娠の可能性がある方は注意が必要です。一方でステロイドや一部の生物学的製剤は妊娠中でも必要最小限の範囲で使用可能です。お薬を飲みながら妊娠してしまった場合には、慌てずに当院にご相談ください。妊娠と薬情報センターでもご相談することができます。
当院では妊娠・出産に備えた治療を専門に相談できる女性外来を設けており、妊娠中の薬剤選択について経験があります。一般に安全とされる薬:サラゾスルファピリジン、ヒドロキシクロロキン、低用量プレドニゾロン、必要に応じてTNF阻害剤など。避けるべき薬:メトトレキサート、レフルノミド、JAK阻害薬など(催奇形性や流産リスクが指摘されています)。妊娠計画がある場合は事前に主治医と相談し、可能なら病状を安定させてから安全な薬に切り替えて妊娠するのが理想です。妊孕性(にんしんしやすさ)の問題でどうしても妊娠を優先させたい場合は、選択するお薬次第でご相談いただくことも可能です。妊娠中も自己判断で薬を中断せず、産科とも連携しながら治療を続けていきましょう。
不妊治療や妊活の相談も可能ですか?
可能です。当院の女性専門外来では、将来の妊娠希望や現在不妊治療中の方の相談にも対応しています。リウマチの患者さんが安全に妊娠・出産できるよう、婦人科や生殖医療科とも連携しながら治療計画を立てますので、遠慮なくご相談ください。リウマチ患者さんの中には、「リウマチだから妊娠は難しいのでは」と心配される方もいますが、近年は適切に病勢コントロールすれば妊娠・出産は十分可能です。不妊治療(体外受精など)を行う際も、リウマチ治療との両立が図れるようサポートいたします。具体的には、不妊治療の期間中だけ一時的に薬を調整したり、排卵誘発剤による関節症状の変化に注意したりします。また、パートナーが男性でリウマチ治療中の場合も、服薬が精子に与える影響など相談可能です。
妊活中の悩みは一人で抱えず、ぜひ専門外来でご相談ください。
女性医師に診てもらいたいのですが?
当院には女性のリウマチ専門医が在籍しており、診察をご希望いただけます。受付時に女性医師希望の旨をお伝えください。予約状況によりますが可能な限り対応いたします。デリケートな症状やライフイベント(妊娠・出産、更年期など)のご相談は、女性医師の方が話しやすいという患者さんも多くいらっしゃいます。希望があればお気軽にご相談ください。患者さんがリラックスして受診できるよう配慮いたします。
出産後や授乳中の治療はどうなりますか?
出産後はホルモンバランスの変化でリウマチが再燃しやすい時期です。そのため、必要に応じて出産前に中止した薬を再開したり、新たに治療を強化することがあります。
授乳中でも比較的安全に使える薬がありますので、母乳育児を希望される場合は主治医に伝えてください。お子さんへの影響を最小限に、かつお母さんの症状をしっかり抑える治療計画を立てます。産後の治療では、お母さんの体調回復と授乳への影響を考慮して薬剤を選択します。例えば、メトトレキサートは授乳中も禁忌なので出産後も避け、主治医と小児科医が連携し、母子ともに安全に治療継続できるようサポートしますので、不安なことは何でも相談してください。
症状・診断について
関節が痛くてこわばります。もしかしてリウマチでしょうか?
関節の痛みや朝のこわばりは、関節リウマチ(RA)の代表的な症状です。
とくに朝起きたときに指がこわばって動かしにくい場合はリウマチを疑います。ただし、関節痛の原因は他にもありますので、自己判断は禁物です。症状が続くようなら早めに専門医を受診しましょう。関節リウマチでは免疫の異常により関節に炎症が起こり、痛み・腫れ・こわばりを引き起こします。放置すると半年以上で関節の骨が溶け出し変形が始まることもあるため、違和感を覚えたらできるだけ早く(症状開始から8~12週間以内が目安)受診し、必要なら治療を開始することが重要です。早期に適切な治療を行えば、発症前と同じような日常生活を送ることも可能になっています。
リウマチ因子や抗CCP抗体が陰性でも、リウマチになることはありますか?
はい、可能性があります。関節リウマチの患者さんのうち約10%程度は「血清陰性関節リウマチ」といって、リウマチ因子(RF)や抗CCP抗体が陰性でも関節リウマチを発症します。血液検査で典型的な抗体が検出されないタイプのリウマチも存在します。この場合でも関節の症状や画像検査所見などから診断し、治療を進めます。したがって、血液検査が陰性でも症状があればリウマチ専門医の評価が必要です。
血液検査で「リウマチかも」と言われましたが、どうすればいいですか?
血液検査でリウマチの可能性を示唆されたら、専門医による詳しい診断を受けることをお勧めします。関節リウマチの診断には、症状の経過や関節の診察、追加の血液検査、画像検査(レントゲンやエコーなど)を組み合わせて総合的に判断します。血液検査だけで診断が確定するのは60~90%程度であり、検査値だけでは決められない場合もあります。早期発見・早期治療が重要ですので、疑われた段階で放置せずリウマチ科を受診しましょう。専門医は問診・触診で関節炎の有無を確認し、必要に応じて関節エコーなど最新の画像検査で炎症の有無を詳しく調べてくれます。検査結果によってリウマチ以外の病気の可能性も評価しますので、「リウマチかも」と言われたらまず専門医に相談してください。
家族にリウマチや膠原病の人がいます。私もなる可能性は高いですか?
家族にリウマチや膠原病の方がいる場合、遺伝的な要因により一般の方よりリウマチになる素因はやや高いと考えられます。ただし、必ず発症するわけではありません。生活環境要因(例:喫煙、歯周病など)も発症に関与します。関節リウマチは一卵性双生児でも両方が発症するとは限らないように、遺伝だけで決まる病気ではありません。遺伝的背景+環境要因(タバコや感染症、ストレスなど)が組み合わさって免疫のバランスが崩れることで発症すると考えられています。家族に患者さんがいる場合はリウマチを念頭に置きつつ、禁煙や歯周病治療などリスクを減らす生活を心がけ、症状があれば早めに受診すると良いでしょう。
関節が変形してきた気がします。どうしたらいいでしょうか?
関節の変形がみられる場合、関節リウマチの炎症が長く続いた結果である可能性があります。まずは主治医に相談し、治療内容の見直しや強化を検討してもらいましょう。進行を食い止めるために、薬剤の調整に加えてリハビリ療法を行うことがあります。変形が高度な場合には、整形外科的手術で機能改善を図る選択肢もあります。 関節リウマチでは炎症が続くと骨が侵食され、関節の変形を起こすことがあります
。近年の治療で変形まで至る患者さんは減りましたが、もし変形が始まっていても、治療を諦める必要はありません。症状に合わせて薬を変更・追加し炎症を抑えることが最優先です。また、こわばりで可動域が落ちた関節に対してはリハビリで筋力や動きを改善し、日常生活指導により、誤動・過動による機械的な負担による変形も予防します。手指の腱断裂や重度の変形には手術的治療(人工関節置換など)で痛みや機能を改善できる場合もあります。
痛みやこわばりはあるのに「リウマチじゃない」と言われました。何が原因ですか?
関節の痛みやこわばりを起こす病気は関節リウマチ以外にもいくつか考えられます。例えば、加齢に伴う変形性関節症(いわゆる軟骨のすり減り)や、線維筋痛症(全身の痛みとこわばりを生じる病気)、更年期障害による関節症状などです。また、関節リウマチに非常によく似た症状を示す他の膠原病(例:全身性エリテマトーデスや乾癬性関節炎など)の可能性もあります。リウマチ専門医は、痛む関節の部位や検査所見から他の疾患との鑑別も行います。例えば指の第一関節(DIP)が痛む場合は、RAよりもヘバーデン結節(変形性関節症)や乾癬性関節炎を疑います。血液検査で炎症反応が強くない場合は、筋肉の痛み(筋痛症)や腱の炎症が原因のこともあります。一方、症状が典型的でも血液検査が陰性の血清陰性リウマチもあるため、一度「リウマチじゃない」と言われても症状が続く場合は別の専門医に相談(セカンドオピニオン)すると安心です。
炎症や腫れは無いのに、痛みだけがあります。リウマチ以外の痛みかもしれませんか?
炎症や腫れがないことはいい事です。
しかし、痛みは炎症や腫れ以外でも起こります。
加齢による変形や事故や怪我などで傷めた部分の痛みが、使いすぎや冷え、気圧の変化で出てくることもあります。
C反応性タンパク(CRP)が陰性ですが、治療しなくても大丈夫ですか?
CRP陰性でも油断は禁物です。
CRPは炎症の指標ですが、関節リウマチではCRPが正常範囲でも関節炎が潜んでいることがあります。症状や関節の腫れがある場合は、CRP陰性でも治療が必要なことがあります。CRP陰性とは炎症の程度が血液上は低いという意味ですが、関節リウマチの活動性を評価する際はCRPだけでなく関節の腫れ・痛みの数や医師の診察所見など総合的に判断します。CRPが正常でも、例えば朝のこわばりや関節の圧痛が残っていれば、完全に炎症が治まったとは言えません。治療の判断は「症状があるか」「関節破壊の進行リスクがあるか」で行いますので、CRP値だけで自己判断せず、主治医と相談して治療方針を決めましょう。
検査でリウマチ因子や抗CCP抗体が高いと言われましたが、放っておいてもいいですか?
放置はお勧めできません。
リウマチ因子(RF)や抗CCP抗体が高値ということは、将来的に関節リウマチを発症するリスクが高いことを意味します。現時点で関節炎の症状がなくても、リウマチ専門医の評価を受けて経過を監視することが望ましいです。抗CCP抗体は関節リウマチに特異的な抗体で、陽性の場合は将来リウマチを発症する可能性が高いとされています。症状がない段階(無症候性抗体陽性)でも、定期的に関節の状態をチェックし、少しでも関節炎の兆候が出たら早期に治療を始めることで関節破壊を予防できます。また、必要に応じて関節エコー検査で微細な炎症の有無を確認することも有効です。検査値が高いまま放置して関節炎が進行すると、後から治療しても関節のダメージを完全には元に戻せない場合がありますので、専門医と相談しながら経過観察するようにしましょう。
子どもが熱や体の痛みを繰り返しています。小児リウマチかもしれませんか?
お子さんでも、若年性特発性関節炎(JIA)など小児のリウマチ性疾患を発症することがあります。
繰り返す発熱や関節痛がみられる場合、小児科または小児リウマチ専門医に相談してください。当院でも0~15歳以下を対象とした小児リウマチ・膠原病外来を開設しています。小児のリウマチにはいくつかのタイプがあります。発熱と全身の関節痛を主症状とする全身型JIA(旧称: 小児スティル病)は、夕方から夜に高熱が出たり発疹を伴うことがあります。また、関節のみ腫れる型や、数カ所の関節が痛む型など様々です。大人の関節リウマチと異なり子供の場合は成長痛など他の原因も考えられるため、専門医が慎重に診断します。ポイントは、発熱や痛みを繰り返す場合は早めに専門機関を受診することです。適切な治療で症状をコントロールし、成長への影響を最小限に抑えることができます。
治療全般について
リウマチは治るのでしょうか?
リウマチは一度発症してしまったら一生付き合っていく病気と言えます。
ただし、寛解という状態になり症状が全くなくなることは可能です。
薬を飲まなくても大丈夫になるか?という点についてはゼロではないが難しいと思います。
痛みがなくなったら治療をやめてもいいですか?
自己判断で治療を中止するのは危険です。
痛みが軽減しても病気そのものが治った(根治した)わけではないので、主治医と相談せずに薬をやめてしまうと再燃(再び悪化)する可能性が高いです。症状が良くなっている場合でも、医師の指示のもとで少しずつ減薬するのが基本です。関節リウマチは寛解(症状が出ない良い状態)を目指す疾患ですが、寛解に達しても治療を継続することが推奨されます。急に薬をやめると、せっかく抑え込んだ炎症がまたぶり返して関節にダメージを与える恐れがあります。医師は症状や検査結果を見ながら、必要最低限の薬に調整していく(減量・休薬を試みる)ことがありますが、それも慎重に判断されます。「痛みがない=治った」ではありませんので、勝手に中断せず、必ず医師と相談しましょう。
寛解(かんかい)って何ですか?
寛解(かんかい)とは、病気の症状がほとんど無くなり、検査上も異常がほぼ認められない状態を指す医学用語です。患者さんにとっては「治った」と感じるような非常に良好な状態ですが、完全に病気が無くなったわけではないので経過観察や治療の維持は続けます。解説: 関節リウマチにおける寛解は、具体的には以下のような要素で判断されます。
・患者さん自身が感じる症状の程度(痛みや不調の自己評価)
・医師が診察して数える圧痛関節数・腫脹関節数
・血液検査の炎症反応(CRPや赤血球沈降速度など)
これらをスコア化し、定められた基準より低ければ「寛解」と判定します。寛解は治療の大きな目標であり、この状態を維持できれば関節破壊の進行もほとんど抑えられます。中には治療せず自然に寛解する例(自然寛解)もありますが、一般的には治療によって寛解に導くことを目指します。
薬の種類が多くて分かりません。どう選べばいいですか?
リウマチの薬には痛みを和らげる薬、炎症を抑える抗リウマチ薬(csDMARD)、さらに生物学的製剤(bDMARD、bsDMARD)やJAK阻害薬(tsDMARD)など多くの種類があります。
治療薬の選択は患者さん一人ひとりの病状に合わせて医師が提案し、患者さんと相談の上で決定します。基本的には、まずメトトレキサート(MTX)などの従来型DMARDを用いて、それで効果不十分なら生物学的製剤やJAK阻害薬を追加・変更するという流れが一般的です。 患者さんによって病気の活動性や生活背景が異なるため、「この薬が絶対」というものはありません。主治医は最新のガイドラインやこれまでの経験を踏まえて複数の選択肢を提示してくれるでしょう。例えば「なるべく注射は避けたい」などの希望があれば遠慮なく伝えてください。治療の基本は患者さんの合意のもとに進めることです。薬の効果だけでなく副作用や通院間隔、費用も考慮しながら、納得できる薬を一緒に選んでいきましょう。
免疫を抑える薬は怖いですが、本当に大丈夫ですか?
自分の免疫が異常に高まっている状態ですので、その治療は免疫を抑えるものになります。
生物学的製剤(バイオ)やJAK阻害薬など、新しい薬も試したいのですが?
生物学的製剤やJAK阻害薬は、近年のリウマチ治療を大きく進歩させた新しいお薬です。
当院では現在使用可能なすべての生物学的製剤・JAK阻害薬を取り扱っており、必要に応じてこれらを用いた治療が可能です。生物学的製剤とは、炎症を引き起こすサイトカイン(免疫物質)の働きをピンポイントで阻害するタンパク質製剤です。一方、JAK阻害薬は細胞内のシグナル伝達をブロックして炎症を抑える飲み薬です。これらは非常に効果が高く、多くの患者さんで関節リウマチを寛解に導いています。ただし費用や感染症などの副作用リスクもあるため、従来の治療で効果不十分な場合や病状が重い場合に使用することが一般的です。興味がある場合は主治医に相談してください。患者さんの状態を評価した上で、メリットが副作用リスクを上回ると判断されれば新しい薬への切り替えを検討します。当院ではこれら最先端の治療薬を一通り使える体制がありますので、安心してご相談ください
治療はずっと同じでいいのですか?時々見直す必要はないですか?
関節リウマチの治療は経過に応じて定期的に見直すことが大切です。同じ治療で症状が安定しているなら継続しますが、病状の変化や新しい治療法の登場に合わせて治療方針を調整します。
医師は診察ごとに疾患活動性(痛みの有無、関節の腫れ、検査値など)を評価し、目標(寛解または低疾患活動性)に達していなければ治療強化を検討します。現在のリウマチ治療はTreat to Target(目標に向けた治療)といって、寛解や低活動性を目指して治療をこまめに調整する考え方が主流です。したがって、治療開始後も少なくとも数ヶ月ごとに状態を評価し、必要があれば薬の種類や量を変更します。逆に症状が落ち着いて寛解状態が安定していれば、薬を減らすことも検討します(ただし勝手に減らさないようにしましょう)。このように、治療は一度決めたら終わりではなく、定期フォローアップの中で最適化されていくものです。主治医と相談しながら、常にベストな治療内容を模索していきましょう。
治療を中断したり、自己判断で薬を減らすとどうなりますか?
治療の中断や自己判断の減薬は非常に危険です。関節リウマチは治療を止めてしまうと再び炎症が活発化し、関節破壊や変形が進行するリスクがあります。
症状が落ち着いていても医師の指示なく薬を減らすべきではありません。一度悪化すると元の状態に戻すのが難しくなる可能性もあります。リウマチを無治療のまま放置すると、激しい痛みや関節の破壊が進み、手術が必要になるケースもあると報告されています。治療を自己中断すると、この無治療の状態と同じリスクを背負うことになります。また、せっかく寛解状態だったものが再燃すると、再度寛解に戻すまでに以前より強い薬が必要になったり副作用のリスクも高まります。経済的・心理的な理由で治療継続が難しい場合も、主治医に相談すれば薬の調整や公的支援の活用など解決策を考えてくれますので、勝手に中止せずまずは相談してください。
「治験」って何をするのですか?
「治験(ちけん)」とは、新しい薬や治療法の有効性・安全性を確認するために患者さんに協力いただいて行う臨床試験のことです。治験に参加すると、まだ承認前の新薬や最新の治療を受ける機会がありますが、同時に副作用や効果が不明な部分もあるため厳重な管理下で進められます。治験は通常いくつかの段階(第I相~第III相試験)に分かれ、少人数の健常者や患者で安全性を確認する段階から、大規模に患者さんで有効性を検証する段階まであります。参加は本人の自由意思で行われ、同意説明(インフォームドコンセント)を十分受けた上で開始されます。治験期間中は担当医や治験コーディネーターが経過を丁寧に観察し、副作用が出た場合には適切な対処がなされます。治験に参加することは将来の患者さんのためになる医学の発展への協力でもありますが、メリット・デメリットをよく考えて決める必要があります。当院で治験を希望される場合は、その時点で参加可能な治験があるかどうか含め主治医にご相談ください。
最新・最先端の治療を受けたいのですが、可能ですか?
可能です。
当院では国内で認可されているすべての最新治療薬(生物学的製剤、JAK阻害薬など)を使用できます。さらに、必要に応じて高度医療機関とも連携し、最先端の治療を提供できる体制を整えています。リウマチ治療の世界は日進月歩で、新薬や新しい治療法(例えば白血球除去療法などの生物学的ではない新規療法)が登場しています。当院はリウマチ専門クリニックとして常に最新情報をアップデートしており、認可された薬剤はすべて導入可能です。例えば「○○という最新の薬を試したい」といった希望があれば、主治医にお伝えください。ただし患者さんの状態によっては適さない場合もあるため、主治医とよく相談して最善の治療法を選択します。また、まだ保険承認前の治療については治験や高度医療機関での先進医療として受ける必要がありますが、その際も紹介などサポートいたします。
今の病院では病名を教えてもらえない、または説明が不十分です。どうすればいいですか?
患者さんには自分の病状を知り、説明を受ける権利があります。現在の主治医の説明が不十分に感じる場合は、遠慮せずに疑問点を質問したり、「病名を具体的に教えてほしい」と依頼して構いません。それでも納得できない場合、別の医師の意見を聞く(セカンドオピニオン)ことも検討しましょう。
当院では「患者さんの持つ権利」として、病気について理解できる説明を受け、必要な情報提供を受ける権利が明示されています。医師側も専門用語をなるべく避け、患者さんが理解・納得できる説明をする責任があります。もし現担当医とのコミュニケーションに不安がある場合、同じ病院の他の医師に相談したり、紹介状を書いてもらって他院で意見を求めることができます。大切なのは患者さん自身が病気と向き合えるよう、情報を得ることです。不明点をメモしておき診察時に確認する、信頼できる医療者に同席してもらう、なども有効でしょう。
正しく診断してもらうにはどうしたらいいでしょうか? セカンドオピニオンは?
正確な診断を受けるためには、リウマチ膠原病の専門医に診てもらうことが重要です。
現在の診断に不安がある場合、セカンドオピニオン(保険適用外)を求めるのは有効な手段です。別の医療機関の専門医に今までの検査結果や経過を見てもらい意見を聞くことで、診断や治療方針への理解が深まります。 セカンドオピニオンを受ける際は、今かかっている先生に紹介状や検査データを用意してもらう必要があります(診療情報提供書も必須)。当院でもセカンドオピニオン外来を行っていますので、希望される場合はお問い合わせください。セカンドオピニオンは「今の主治医に不満があるから変える」ということだけではなく、納得して治療を続けるための情報収集と考えると良いでしょう。
一方で医師ごとに見解が異なる場合もありますが、その場合は遠慮なく疑問を質問し、自分が理解・納得できる説明をしてくれる医師を選ぶことも大切です。
検査・画像診断(エコー・レントゲンなど)
関節エコーでは何が分かるのですか?
リウマチ性疾患では関節に炎症を起こしたり、骨が破壊されてしまったりすることがあります。
それをエコーを使ってみることができます。
エコー画像で赤く映っている部分は何ですか?
血液がたくさん流れている所は赤くなります。血管には血液が流れているので赤くなりますが、関節の中は流れていません。関節の中が赤くなると炎症と判断します。
被ばくが心配なのでレントゲンは撮りたくありません。問題ないですか?
検査で使用するX線量はごく微量です。胸部レントゲンを撮影するのと、飛行機で海外旅行するのとを比べると胸部レントゲンは飛行機で旅行した時の10分の1の量です。
痛みがないのにエコーやレントゲンを撮るのはなぜ?
リウマチ性疾患は治療が上手くいくと痛みや腫れを感じにくくなります。ただ、痛みや腫れが無くなっても病気が進行していことがあります。それを確認するために検査を行います。
エコー検査で病気がわかりますか?
一つの検査で病気が分かることはありません。ただ、現在の痛みの原因や炎症の程度などはエコー画像から判別することができます。
炎症が残るとどうなりますか?
エコー検査では炎症の程度を知ることができます。骨の近くに炎症が残っていると骨破壊が起こります。腱や靭帯に炎症が残っていると切れてしまう恐れがあります。炎症の程度を確認することで治療法が変わります。
リハビリ・サポート体制
リウマチにリハビリは必要ですか?
関節リウマチによる炎症は関節を不安定にします。また炎症による痛みから動く機会が減少し、筋力低下も招きます。薬を使用して炎症を抑えても、関節や筋肉の機能は改善しません。リハビリを行い、低下した機能を再獲得することが必要となります。
また関節リウマチの炎症はどの関節に生じるのか前もって知ることができません。そのため現時点で痛みがなくとも身体全体の機能を高めておくことが、関節リウマチの痛みに対するコントロールとして大切になります。
どのような場合にリハビリを受けたほうがいいのでしょうか?
痛みの有無に関わらず、日常生活に不自由さや手足の使いにくさ、動かしにくさを感じるようであればリハビリを行うことをお勧めします。身体の使いにくさがある場合は、必ずどこかの関節や筋肉の動きが悪くなっています。そのまま放置して生活してしまうと、関節炎や関節変形を増悪してしまう危険性があるため、リハビリが必要となります。
リハビリの頻度はどれくらいが理想ですか?
リハビリの頻度はリウマチの疾患活動性だけでなく、年齢や身体機能の状況、普段の生活環境(仕事や家事など)といった様々な要因を踏まえて判断しています。痛みが強い段階では週1~2回程度実施し、症状が緩和してきたら頻度を減らすなど状況に応じて対応させていただきます。
リハビリをした後に痛みが出た場合はどうすればいいですか?
リハビリでは普段使えていない筋肉を動かすため、実施後に筋肉痛が生じることがあります。筋肉痛であれば2,3日すると軽減します。ただ関節が熱を持って腫れるなど炎症が強くなっている場合は、リハビリでの運動の負荷が強すぎた可能性があります。
その際はアイシングで冷やすように対応してください。症状によって次回以降のリハビリの負荷を調整しますので、ご自身の判断でリハビリを止めず担当のスタッフに症状をお伝えください。
リウマチ以外でもリハビリは受けられますか?
リウマチ以外でもリハビリは可能です。ただリハビリを受けるには適応となる疾患が必要となります。
担当医と相談して頂ければ、症状に応じたリハビリを実施させて頂きます。
インソールはどのような効果がありますか?作製にはどれくらい時間がかかりますか?
歩行時の脚の痛みに対して効果があります。インソールを使用することで歩き方を調整し、関節や筋肉にかかる負担を減らすことができます。そのため足裏の胼胝による痛みだけでなく、膝や足首の痛みの緩和も期待できます。
インソールの作製には身体機能の評価も行います。完成までに4回来院していただく必要があります。
スプリントにはどのような効果がありますか?作製するにはどれくらい時間がかかりますか?
スプリントの効果は、関節の動かせる範囲は残しつつ、変形を予防、動作の改善の効果が期待できます。
作製時間は20分~40分で、当日お渡しが可能です。その後、もし合わないようであれば、再調整が可能です。気兼ねなくお声がけください
リウマチの炎症が落ち着いたら、リハビリも終了して良いのでしょうか?
リウマチの炎症が落ち着いても関節や筋の機能低下が生じている可能性があります。その場合は炎症がなくとも運動時に痛みが生じたり、関節変形が進行するリスクがあります。
リハビリの終了時期は炎症の有無だけでなく身体機能の状態で判断していますので、担当医やリハビリスタッフと相談して決定しましょう。
自宅でできる運動はありますか?
リハビリを受ける時間よりも自宅で過ごす時間の方が圧倒的に長いため、ご自身で行う運動はとても重要となります。しかし適した運動は個人差があります。合わない運動を行うと却って痛みを増悪させてしまう危険もあります。
リハビリではその方の状態に合わせて自宅で行う自主トレーニングも指導させて頂いていますので、一度リハビリを受けて頂くことをお勧めします。
痛みがあっても運動をしても良いのでしょうか?
痛みがある部分に負担が掛かる運動は行わない方が良いです。どうしても行う必要がある場合は、関節を保護するためのサポーターを使用してください。運動そのものは抗炎症作用があるとされているため、痛みのある関節に負担を掛けない運動は行うことをお勧めします。